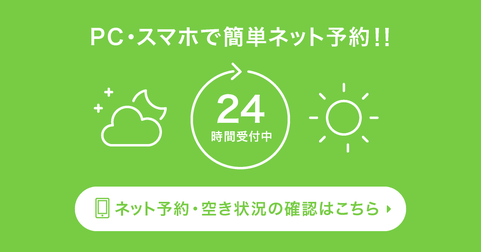ブログの内容は、一ヶ月ほど前の出来事です。
そのため、画像がまだ冬になっています。岐阜では、梅が満開を迎えていますのでよろしくお願いします。

アスラ先生の生徒の授業の時。Hくんは、レッスン前の準備中の際に・・・
「お母さん、ノート持ってきて。」
「ちょっと待って。」
「まだ?ちゃんと、ノートいるって言ったよ。」
よくある会話ですよね。。。。 生徒の言いたいこと、言いたくなることもわかりますが、問題は誰が授業を受けるのか? 何のために授業を受けるのか? ということ。
中国語レベルはとても高く、1を聞いて10を知る ことができます。今は、HSKも受けようと学習しているほどです。そんな優秀なら、このくらいの言い方は、許しても良い?と思いがちです。が、

かおり先生登場
「誰のために、中国語を学ぶんですか?」
「お母さんが、中国語を習うのですか?誰かに何かを頼む時は、もう少し優しい言い方をしたほうが良いのではないですか?」
アスラ先生がレッスンをする前に、かおり先生が指摘。こういったことは、実は・・・今回が初めてではありません。
外国語を学ぶ際に、見落としがちな、母国語の正しい使い方。おもてなし。マナー。オンラインレッスンだと、なおさら必要になりますよね?音声が途絶えたり、通信の速度のトラブルなどなど・・・
対面レッスンでは発生しない事案が多くあるわけですから、親子とはいえ規律を保ちたいものです。

気遣いの上手な保護者
Hくんのお母様は、常々Hくんの話す話し方(日本語)がどうしても気になるようです。
「先生方と、親しく楽しく中国語を学習できることはありがたい一方で、少し言いたいことを言い過ぎてしまうのでは?」
と、時々気遣いをいただいております。
中国語学習において、日本語・中国語で通達する。しかも、オンライン上で・・・ デジタルに長けている子どもたちは、今見る世界が当たり前ですからね。。。
保護者が生きた時代(平成)には、オンライン学習法はほとんどなかったわけです。当たり前のことですが、言語化するとなかなかですね。改めて、考えていただくきっかけになればと思いながら、今回は、オンライン授業という学習スタイルについて、ブログを書いてみます。

新たな時代の対応力
時々、面白い発見があります。
デジタル学習は、アナログ学習とは異なり対象年齢が低いと、アクセシビリティが難しかったりします。そのため、保護者がサポートするわけですが・・ 慎重に、手順を踏んでも難しかったり、予想外のトラブルも続出。あってはなりませんが、あるあるですよね?
そんな時、子どもたちの声も様々です。
「なんでできないの?」
「そんなの簡単なのに・・。」
という声や、
「うちは、ネット環境が悪いかもしれません。」
「ちょっと、待ってください。先生。」
などなど。様々な声が聞こえ家庭の様子がわかるのが、面白い。
この1、2年だけでも、生徒たちのオンライン授業そのものに対しての心得というのも、定着してきたように思います。これは、全体的な話です。とはえ、保護者らのこんな声もあったりします。

過去のことは伝えないとわからない
過去とは、デジタル社会ではなかった頃のことです。
生徒によっては、現在の大人たちもデジタルを使いこなしていたのだ・・ わからないなんてない。大人なんだから・・・と考えて、話をするケースもあります。実際に、一部の生徒からは、このことを話すと、相当驚いていました。思い込みってやつですね。
子どもたちにとって、過去、生まれる前のことを想像するのは難しいのかもしれませんね。ある程度、付随した情報がないと想像すらできない。発展し続ける現在が全てですからね。
「昭和のこと、平成のことなんて・・話たところで、仕方ない。」
なんて思わずに、コミュニケーションのきっかけにもなるかもしれないので、このオンライン授業という文化?オンライン授業の歴史のような話をしたりするのも、世代ギャップがあって面白いように思います。
まずは、声を出すところから

学習した中国語が、すっと声に出せて流暢に会話できることが簡単にできたら良いですが、時間には習得がかかるからこそ面白い。
まずは、日本語からでも良いので伝えたいことがあれば、声に出すところから始めても良いのではないかと思います。その伝えたいことが、たとえ短い言葉であっても。声に出すことで感じるところがある。
感じることができて、初めてワクワクしたり、続けてみたくなる。
そんなふうに思います。
これからの時代は、ある程度はAIに質問できたりして、課題は解決できる環境に整います。人間である以上、特性を活かして超情報化社会でどう言語学習を進めたいか?
生徒たちと一緒に、考えているところです。そして、アスラ先生にもHくんとの人間関係形成に必要なことは、伝えるだけではなく、積極的に気づいたことは、Hくんに指摘するように話をしました。
4月に向けて、また何か楽しいことを企画したなと思っております。
花粉症の季節となりましたので、どうぞご自愛くださいませ。